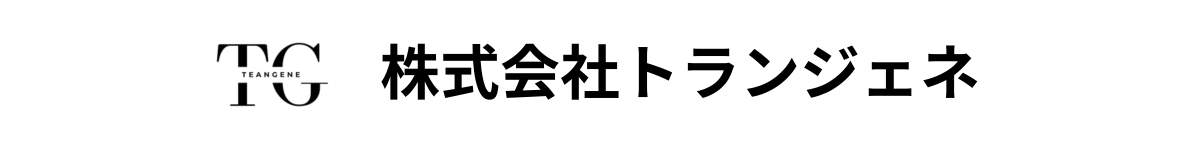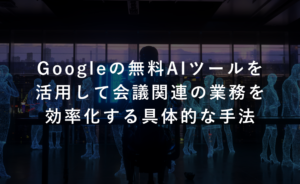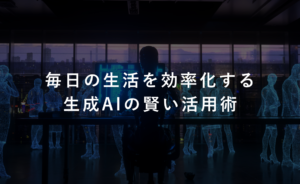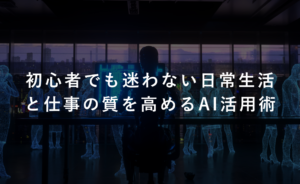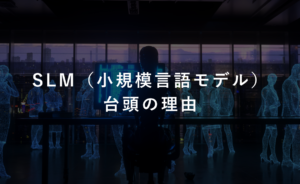生成AIに資料を作らせたり、文章の壁打ちをしたりする中で、こう感じた経験はないでしょうか。「賢くて便利だ。しかし、いくらプロンプトを工夫しても、面白みのないアウトプットを延々と吐き出し続ける…」。
このAIが生み出す「つまらなさ」の正体を探ることは、裏を返せば「人間が何に面白さを感じるのか?」という、私たちの本質を理解する鍵となります。
そこで本記事では、デジタル人類学者としての視点から、AIには生み出せない「面白さ」の正体を3つの要素に分解し、人間だけが書けるコンテンツの核心に迫ります。
1. 「予測」を裏切る“ずれ”こそが面白さの源泉
人間が「面白い」と感じる瞬間、その根源には「予測とのずれ」があります。脳科学では「予測誤差」と呼ばれますが、私たちの脳は常に少し先の未来を予測しながら情報処理をしています。その予測が「少しだけ」裏切られた時に、「おっ?」と興味を惹きつけられるのです。
- 落語のオチで「うわ、そう来たか!」と笑いが込み上げる
- 映画の伏線回収で「うわ、そこに繋がるのか!」と唸る
- 本の一節で「うわ、その発想はなかった」と膝を打つ
これらはすべて、心地よい裏切り、つまり「予測とのずれ」が生み出す快感です。
一方で、生成AIの文章にこの「ずれ」が生まれにくいのは構造的な理由があります。AIは、膨大なデータの中から最も確率の高い、つまり「最も平均的で自然な」言葉のつながりを返すように設計されているからです。
人間が面白さを感じるような「予想を裏切る外れ値的なデータ」は、AIにとっては発見や驚きではなく、処理すべき「ノイズ」と見なされてしまいます。
この構造的な違いこそが、AIの文章が「漏れがなく正確で自然」である一方、「比較的一般論に終始してしまう」根本的な理由です。AIは確率的に最もらしい「正解」を導き出すことには長けていますが、驚きや意外性のある回答を生み出すことには元来向いていないのです。
2. 面白さは頭ではなく「身体」で感じる
次に、面白さの核となる「自己参照性」についてです。私たちは情報に触れたとき、「これは私のことだ」と自分事として捉えた瞬間に、強く心を掴まれます。面白い話は、他人事から自分事になった瞬間に成立するのです。心理学ではこの現象を「自己参照効果」と呼びます。
AIも表面的な共感風の文章を書くことはできます。しかし、人間との間には決定的な違いがあります。それは、AIが「身体」を持たない知性であるという点です。AIは、経験として共感を理解することができません。
人間の共感は、論理的な理解ではありません。「もらい泣き」や「もらいあくび」を思い浮かべてみてください。これらは、相手の感情や感覚を、頭ではなく自分の身体の中で無意識に再現することで起こる現象です。脳内のミラーニューロンなどが関わる、極めて「身体的」な反応なのです。文章から感じる「血が通っている」という感覚は、この身体的なリアリティに根差しています。
AIには痛みも、寒さも、心拍の高鳴りもありません。だからこそ、AIの文章はどこか「響かない」。この響かないという感覚は、実は私たちの「身体」に響いていないということなのです。AIが作った作品を見て、「ちゃん」とつまらないと感じられる人は、クリエイターとしてむしろ健全だと私は思います。これからのクリエイターは、論理的な知性だけでなく、自身の「身体的な知性」を磨くことが一層重要になるのではないでしょうか。
3. 人は「変化のプロセス」に物語を感じる
AIと人間のもう一つの根本的な違いは、「時間」の捉え方にあります。
AIにとって時間とは、あくまでデータが並ぶ「処理順序」に過ぎません。その認識は本質的に、静止画を連続させたパラパラ漫画のように不連続です。
一方、人間は「体験の変化」を通して時間を主観的に捉えます。背が伸びたり、できなかったことができるようになったり、私たちは常に変化し続けながらも「同じ自分である」という自己連続性を持っています。過去も現在も未来も、違う自分でありながら、すべてが同じ自分であるという感覚です。
この「変化」こそが、物語の核となります。体験を設計する上で重要なのは、完成形や正解を提示することではなく、ユーザー自身が「変化していくプロセス」そのものを体験できる設計にすることです。
事例1:林修先生の授業 最近、X(旧Twitter)で話題になったエピソードですが、予備校講師の林修先生が、ある授業でほとんど準備をせずに登壇した際、その授業がかえって学生から好評だったという話があります(真偽の裏取りはしていません)。その日、林先生は生徒と一緒に初見の問題を試行錯誤しながら解いていきました。生徒たちが価値を感じたのは、完成された知識ではなく、「林先生自身がその場で考え、変化していく時間」を共有できたことでした。
事例2:フルーチェ ロングセラー商品の「フルーチェ」は、完成品として売ることもできたはずです。しかし、あえてユーザーが牛乳を加えて「混ぜる」というプロセスを残しています。液体状のものがプルプルに固まっていく「変化そのもの」が、この商品の体験価値になっているのです。
AI時代に人間が担うべき役割は、論理的に正しい情報を提示することではありません。それはAIが得意とするところです。私たち人間に求められるのは、ユーザーが変化を実感できるような、「物語としての主観的な体験設計」なのです。
結論:AI時代にこそ「人間らしさ」を磨く
AIの文章がなぜ「薄っぺらい」のか。この問いを深掘りすることで見えてきたのは、人間が本能的に「面白い」と感じる3つの要素でした。
- ずれ(予測との乖離):心地よい裏切りがもたらす快感
- 身体(身体性):自分事として捉える、身体を通した共感
- 変化(プロセスの体験):変化していくプロセスそのものに感じる物語
AIという鏡を通して、私たちは「人間らしさ」の輪郭をよりはっきりと捉えることができます。これからの時代、本当に価値あるコンテンツを生み出す鍵は、この人間的な感覚をいかに理解し、磨き、表現していくかにかかっているのかもしれません。
あなたが「面白い」と感じる瞬間には、この3つのうちどの要素が隠れているでしょうか?